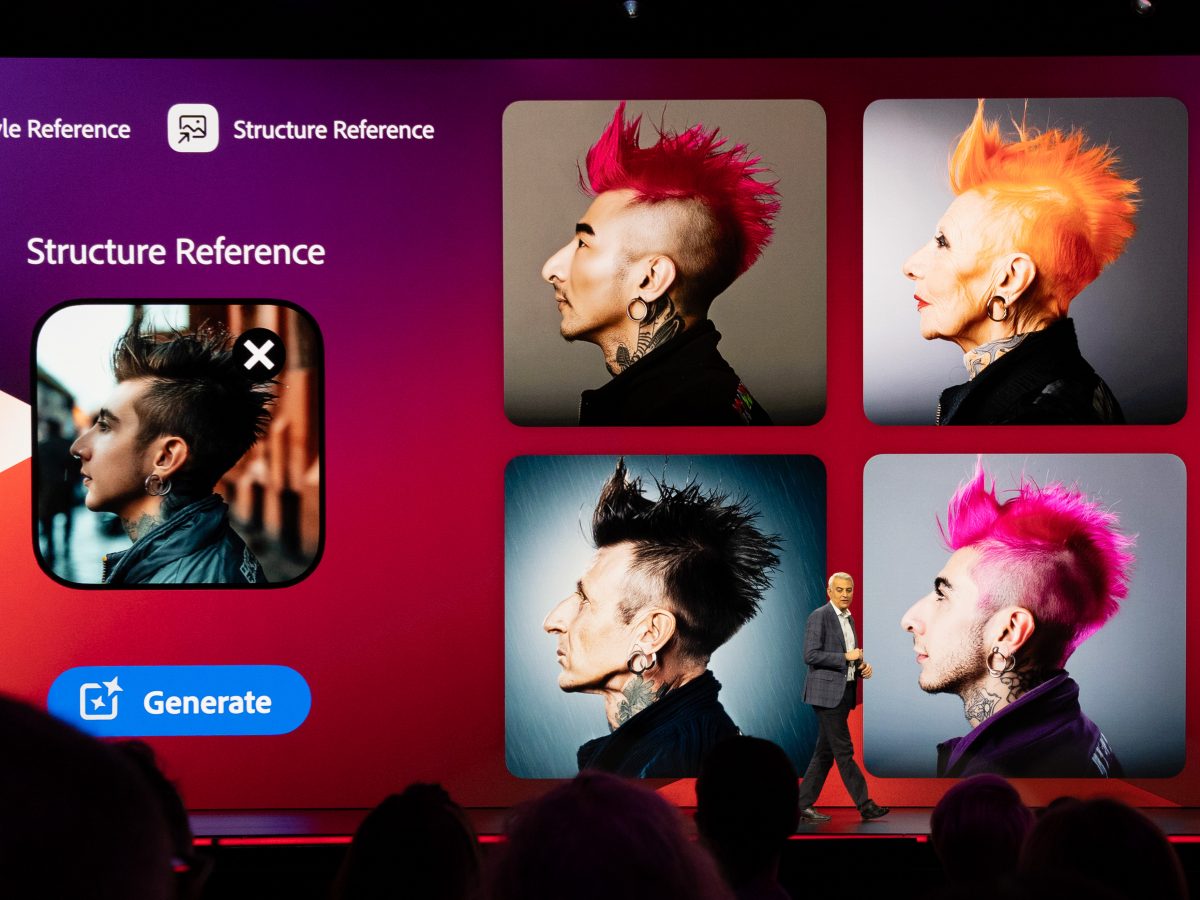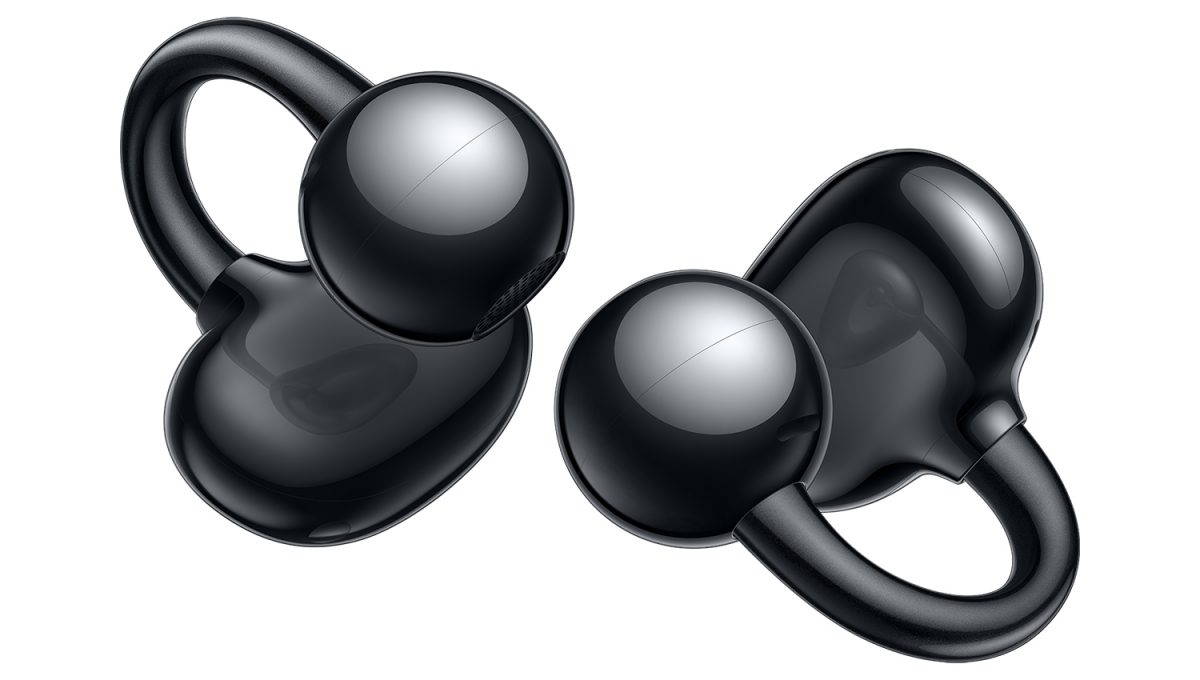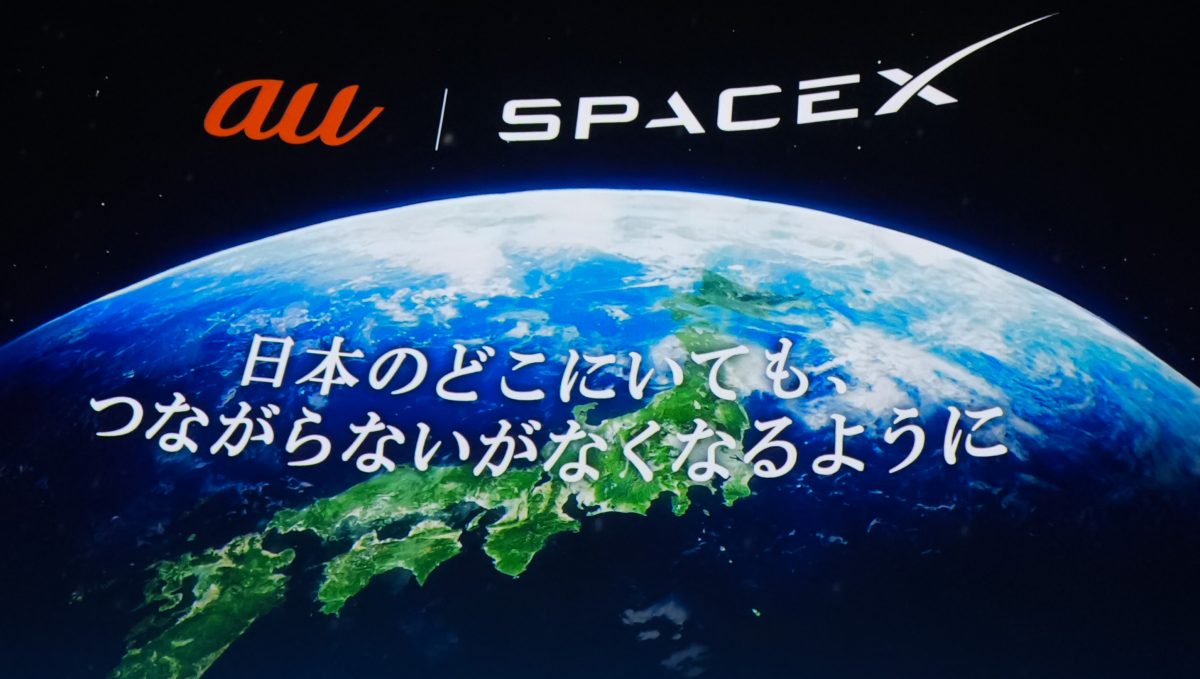Vol.151-4
本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はGoogleが公開したAIを活用したスマートグラス「Android XR」の話題。これまでのスマートグラスと異なる点と新たな可能性を探る。
今月の注目アイテム
AI活用型スマートグラス
価格未定

Android XR対応のデバイスとして、最初に世の中に出てくるのは「Project Moohan」だ。
前回の本連載で説明したように、Project MoohanはApple Vision ProやMeta Questの対抗製品という位置付けに近い。Google Playストア経由でAndroidアプリが使えて、Googleのサービス群がXR空間の中に最適化された形で用意されるのが大きな特徴。Vision ProとMeta Questそれぞれの要素をうまく取り入れた製品、という印象だ。
ただ、Android XRは複数形態のデバイスを開発できるプラットフォームとして作られており、Project Moohanのような「ヘッドセット型」はひとつの形でしかない。
このほかにGoogleは、「光学シースルー型ヘッドセット」「ARグラス」「AIグラス」を典型的なデバイスとして挙げている。
光学シースルー型は、Project Moohanに違いがビデオシースルーでない分、より簡易でコンパクトな製品になる。近い存在として、中国のXREALは「Project Aura」を開発中と公表している。グラス型のデバイスとなんらかの“本体”をケーブルでつないで使うもので、20206年以降の発売を目指している。
AIグラス・ARグラスは、今回のGoogle I/Oでプロトタイプが発表されている。Androidスマホと連動し、AIで周囲の状況や利用者の命令を受けながら、アシスタントとして働くメガネ型デバイスである。ディスプレイが内蔵されたものがARグラスで、ないものがAIグラスと考えればいい。まだプロトタイプの段階で、2026年以降に製品化の目処が見えてくる、というところだろうか。
実のところ、ここに挙げた4形態はかなり異なる特徴を持っている。Project MoohanとディスプレイのないAIグラスでは、必要なインターフェースも処理に必要な性能も大きく異なってくるし、全く同じアプリケーションを動かすのは難しい。開発手法自体も異なるだろう。開発者からは“それをひとつのプラットフォームでくくるのはある意味強引な話”という意見も聞こえてくる。
ただ、Googleは“開発の一貫性に配慮している”と説明しており、まったく違う開発環境が用意されるわけではないという。そのため、4つの形態それぞれに向いたアプリを、ひとつのサービスやコンセプトから作っていける。そして、同じ“Google Playストアから配信してビジネスができる”のが大きなことになるだろう。
特にProject Moohanのような製品の場合、スマホやタブレット向けの「Androidアプリ」をAndroid XRでも動かせるので、ビジネスチャンスが広がる。
Android XRは、“Googleであること”“Androidであること”を大きく生かしたプラットフォームであることを武器にして、他社と戦っていくことになるわけだ。
週刊GetNavi、バックナンバーはこちら
The post 【西田宗千佳連載】「GoogleのAndroidであること」を最大限に生かすAndroid XR appeared first on GetNavi web ゲットナビ.