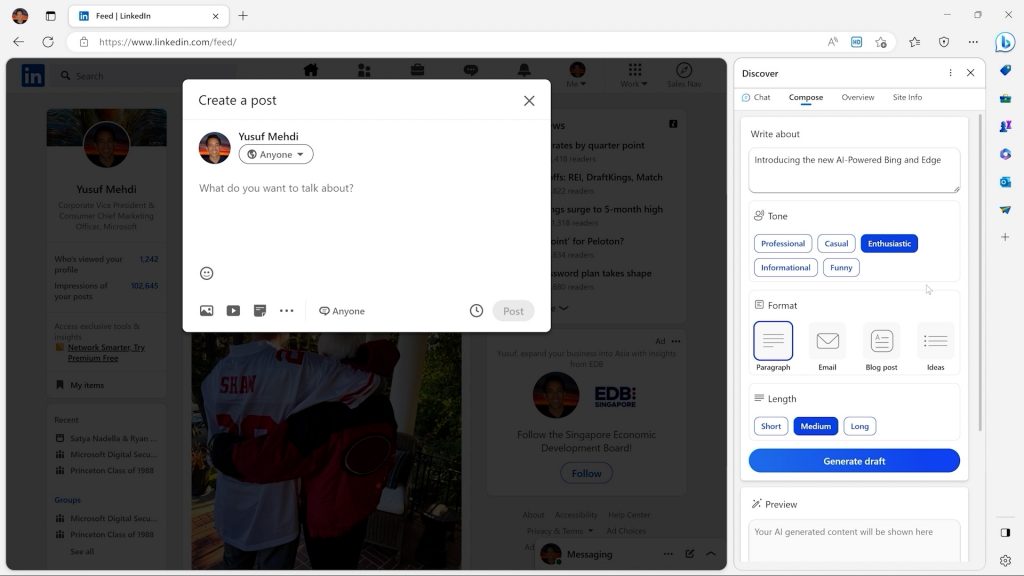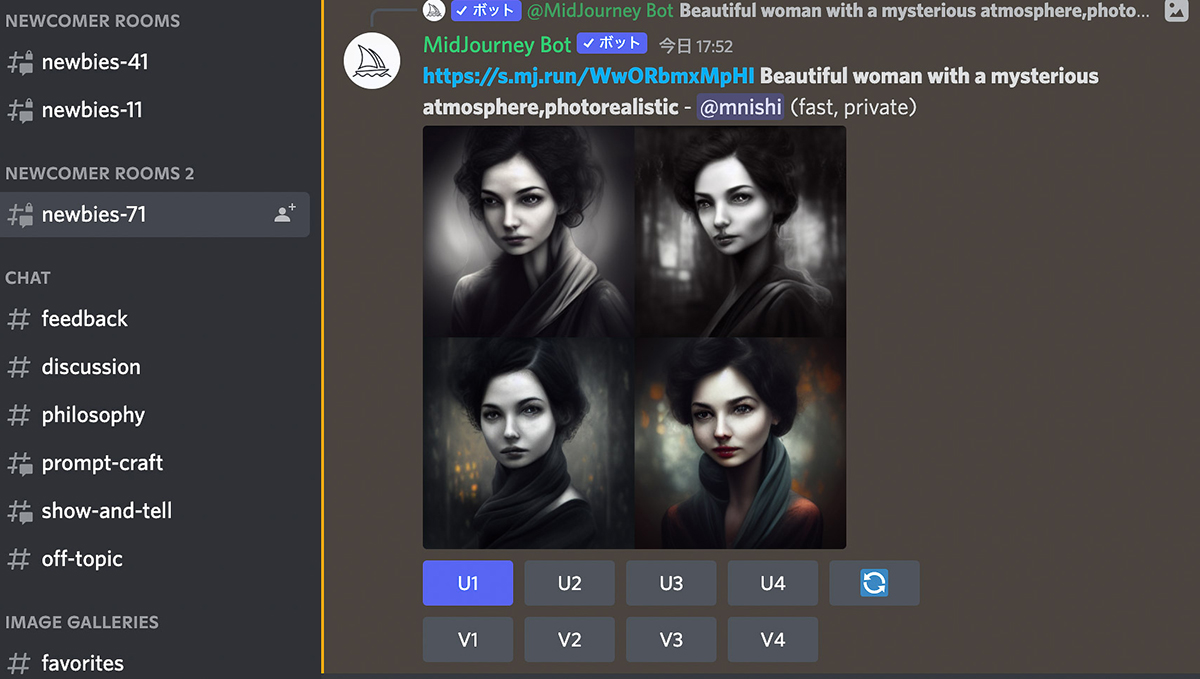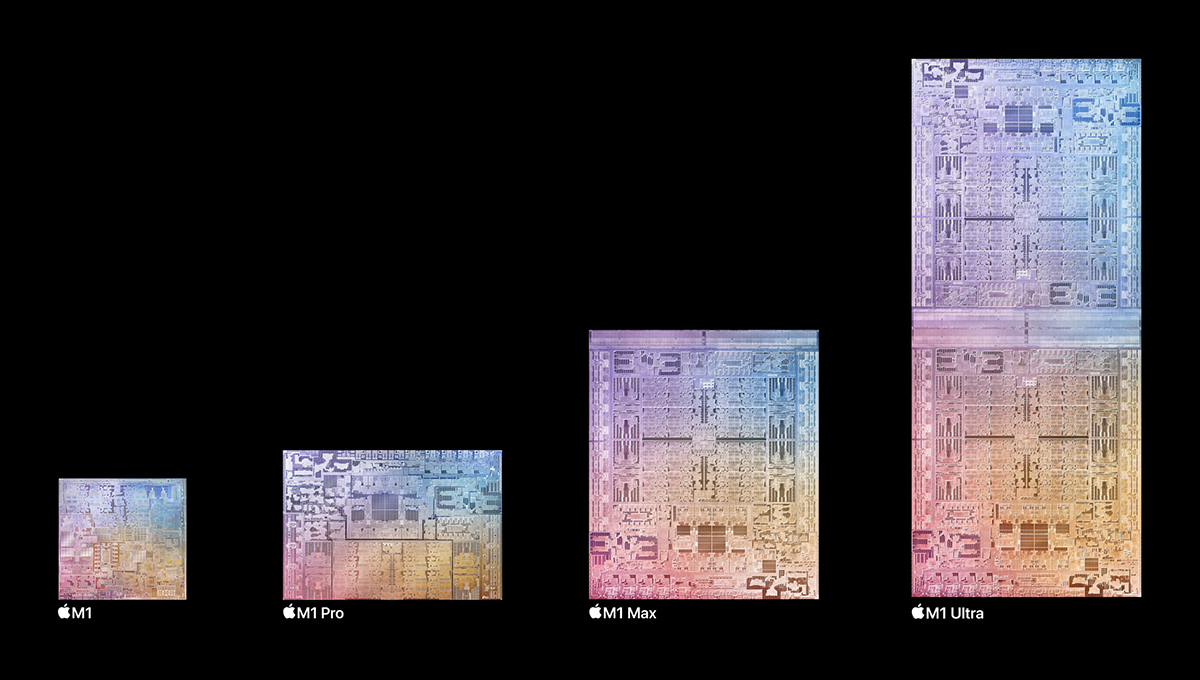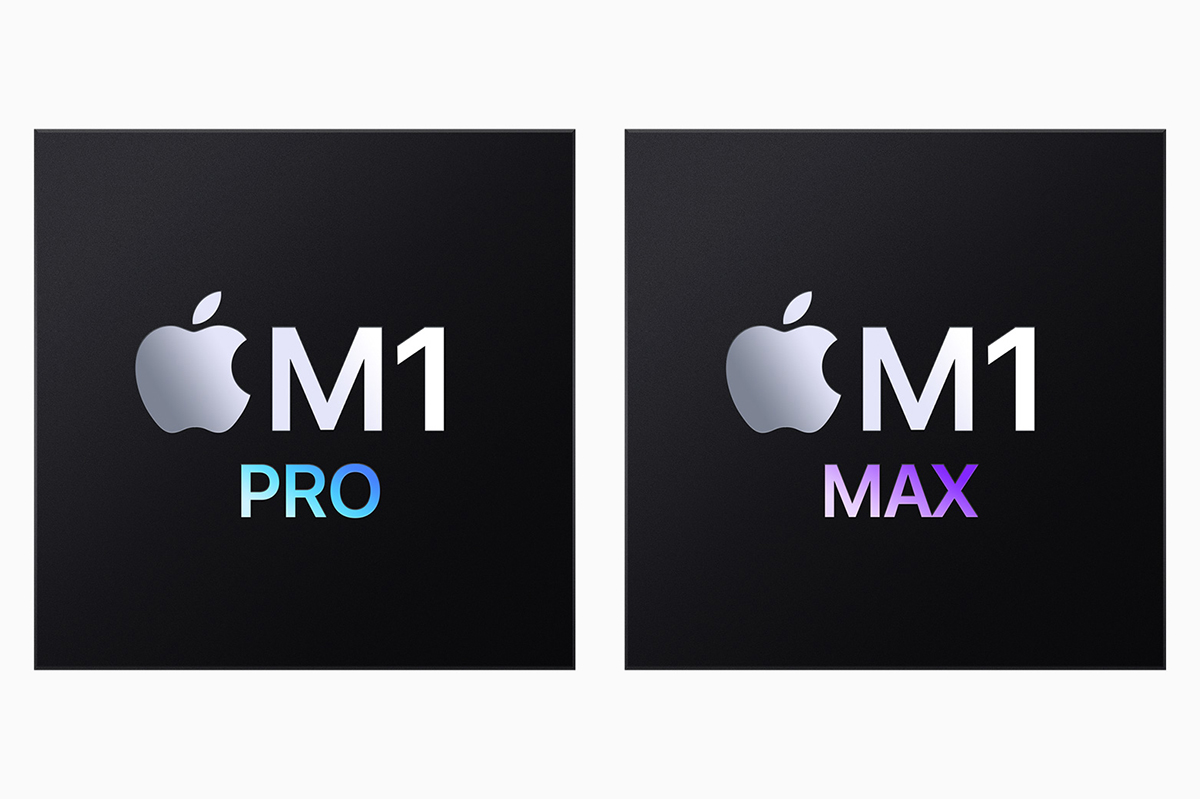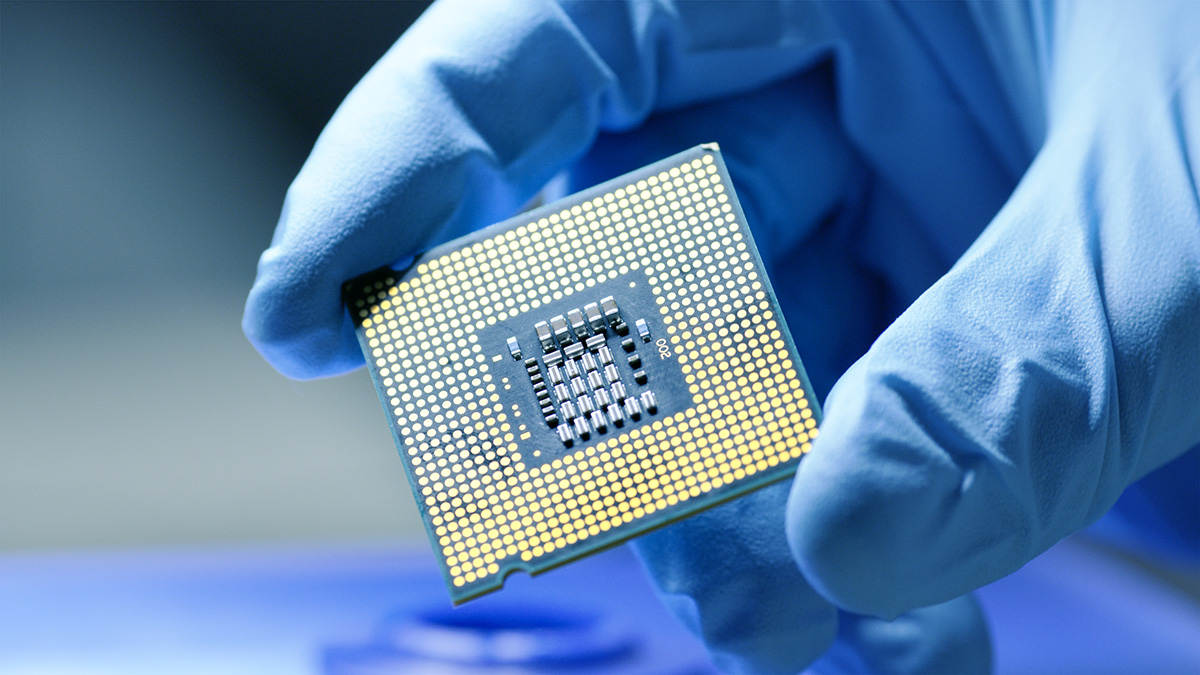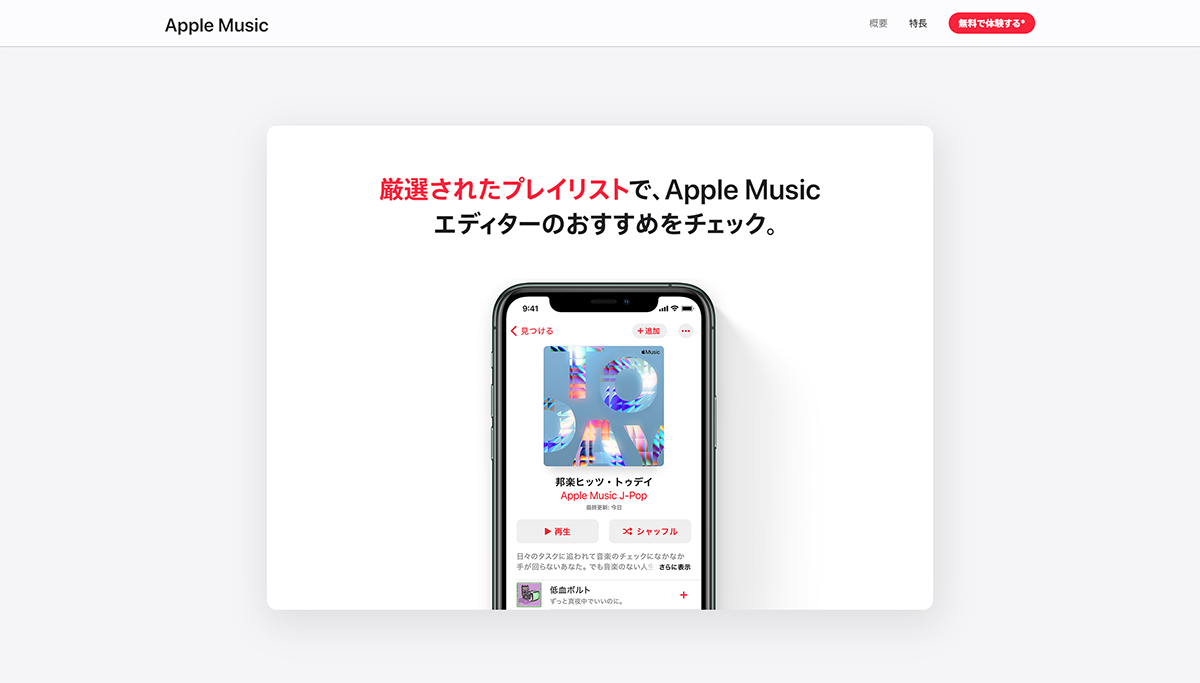Vol.125-3
本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回のテーマはマイクロソフトが発表した検索エンジン「Bing」の進化。ライバルとなるGoogleの動向を解説する。

マイクロソフトがOpenAIとのコラボレーションによって「ジェネレーティブAIの時代」を切り開こうとしている。当然Googleは、そこに対抗していかなければいけない存在だ。
Googleは以前から、独自に大規模なAI開発を行なってきた。その中でまず重視していたのが「画像認識」だ。「Google レンズ」を使うと、外国語で書かれた標識を翻訳したり、写真に写っている花がどんな種類のものなのかを教えてくれたり、といったことができる。
スマートフォンの普及により、我々は常にカメラを持ち歩くようになった。文字入力は重要なことだが、面倒であるのは変わりない。だから、もっと別の手段から検索を可能にし、利便性を高めようとしていたわけだ。
このように、文字だけでなく画像や音声など、多彩な情報を扱うことを「マルチモーダル」と呼ぶ。Googleは特にマルチモーダルな情報の活用に積極的であり、それと大規模言語モデルを使ったAIを組み合わせて、「言語の壁や画像と文字の壁などを取り払い、質問に答えられるサービス」の開発を目指していた。
ただその過程では、大規模言語モデルを使ったチャットAIの危険性にも気づいていた。完全な技術ではないため、間違った答えを出す可能性も高い、ということだ。
どうやらGoogleは、そこで躊躇したようだ。
ネット検索で大きなシェアをもつGoogleには相応の責任がある。本来検索結果は、そのまま鵜呑みにできないものだ。AIが作り出す回答も同様である。
しかし、人はラクをしたいと思うもの。多くのシーンで、ネット検索が出した答えをそのまま信じてしまう。過去、医療情報などで大きな問題が起きたため、Googleは「検索結果の信頼性」に多大なエネルギーを投じ、品質改善にも努めている。そこに不完全なジェネレーティブAIを無理に導入するのは、ここまでの労力を無にしかねない。
また、ネット検索がAIベースになり、検索結果を生み出すことになった記事でなく、「検索結果をまとめたAIの文章」を読んで満足してしまうと、ネットに存在する数多くのWebメディアへの広告収入を奪う結果にもなりかねない。
すなわちGoogleにとって、検索にジェネレーティブAIを組み込むことは、ビジネスと倫理の両面で課題があったわけだ。
一方でマイクロソフトは、ネット検索では明確に「チャレンジャー側」だ。巨大なライバルであるGoogleと戦うには、多少強引でも新しい武器を使って有利な立場を得る必要がある。この差が、現在のGoogleとマイクロソフトの立ち位置を決めている。
AIへの注目は大きいものの、「一般の人々が検索の仕方を変えるには、長い時間がかかる」との指摘もあり、マイクロソフトの目論見がすんなり成功すると言い難い部分もある。
とはいえ、Googleも、ChatGPTに対抗する大規模言語モデルを使ったサービスである「Bard」を発表し、3月21日より、アメリカ・イギリスを対象に、登録ユーザーに向けて提供を開始した。
では、Bardはどんな特質を備えたものになり、どうマイクロソフトに対抗していくのか? その辺は次回解説する。
週刊GetNavi、バックナンバーはこちら