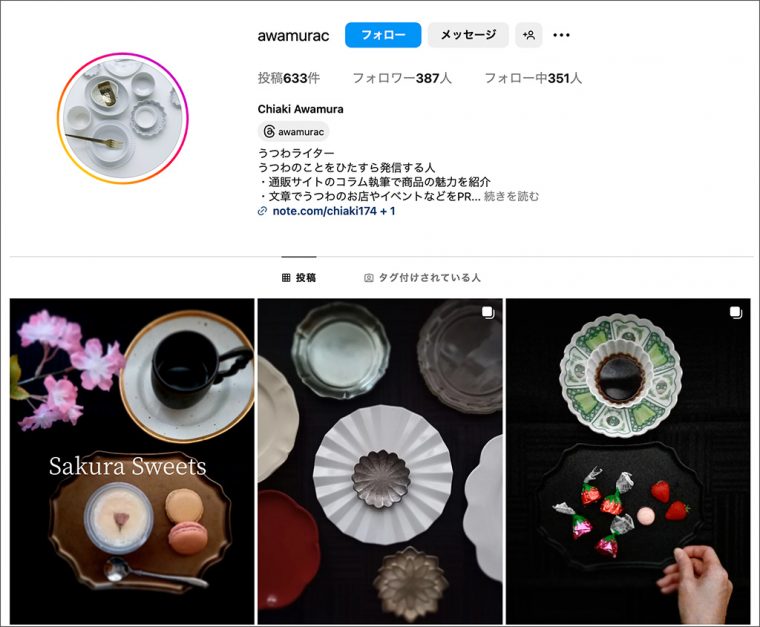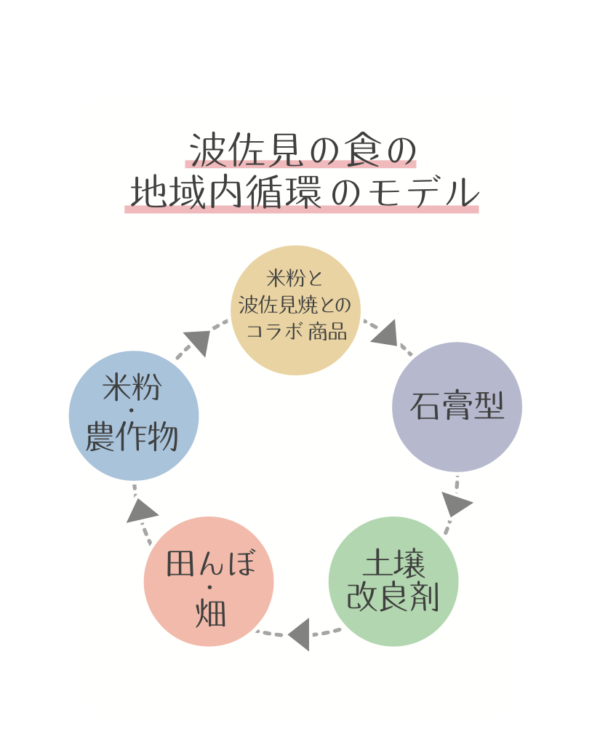長かった冬を超え春本番。ゴールデンウィークも近づきお出かけしたくなる季節の到来です。この春は、おうち時間をより豊かにするアイテムを探しに出かけるのはいかがでしょうか。 いつもの料理が特別に感じられたり、静かなティータイムが贅沢なものに変わったり、暮らしを豊かに彩るアイテムのひとつが“食器”です。
そこで今回は、「うつわ検定」の創設者でもあり、テレビや雑誌の撮影で器などをスタイリングするプロップスタイリストとしても活躍する二本柳志津香(にほんやなぎ・しずか)さんに、食器のトレンドやおすすめのショップなどをうかがいました。プロ直伝の“うつわ選び”のコツをお届けします。
今の時代のうつわ選びは“多様性” お気に入りの作家を“推し活”するトレンドも ↑写真提供:二本柳さん。
ファッションや美容と同じように、うつわにもその時々のトレンドがあります。二本柳さんは、今の時代のうつわ選びのトレンドキーワードは「多様性 」だと言います。
「少し前までは、いわゆる“トレンド”の流行り廃りがありました。たとえば、『ドイツのガラスウェアブランド「Nachtmann」がおしゃれ!』となれば、世代を問わずみんなが『Nachtmann』を買い、1年経って今度は「◎◎◎◎◎◎がいいらしいよ!」となって、みんながそれを買うという時代が続いていました。生活環境やライフスタイルが多様化し、それぞれが自分に合うものを選んで楽しむ時代になってきている ということです」(プロップスタイリスト・二本柳志津香さん、以下同)
↑写真提供:二本柳さん。
右にならえで人気の有名ブランドを買う時代は終わり、自分の目で見て触って、自分だけのお気に入りを探し出す。そんなスタイルが今の時代らしいうつわ選びのようです。
「ECショップが豊富な時代ですが、忘れないでいただきたいのは、うつわは実店舗で選ぶのが楽しいアイテム だということ。雑貨店や商業施設の店頭には、その地域の暮らしに合ううつわが提案されているので、ぜひ家の近くのお店に足を運んでみてください 。実際に見て触って、テイストや質感、重さなど、『私の家に合うかな?』と考えながら、目利きすることも“うつわ選び”の醍醐味です 。普段の食卓や食器棚の写真を見せながら、『こういう食器を集めています』、『こういう暮らしをしているのですが、我が家に合いそうなものはありますか?』とお話しながら探すのも楽しみ方のひとつ です」
↑写真提供:二本柳さん。
お気に入りの一枚に出会えると、作家の“推し活”へ発展することもあるのだとか。
「うつわ好きの方のなかには、好きな作家の個展へ行くのを楽しみにしている方がたくさんいます。なかでも豆皿を集めるのがちょっとしたブームになっている のを感じますね。大きいお皿だと高価で気軽には買えませんが、豆皿であれば比較的低価格で集めやすい。これが人気の理由かと思います。流行り廃りよりも自分のお気に入りの作家のうつわを集めること が、トレンドのひとつとも言えるでしょう」
二本柳さんの元で活動する、うつわライターの粟村千晶 さんもInstagramやnoteなどでも推しの作家を紹介しているそうです。
↑粟村千晶さんのInstagram。
自分だけのお気に入りに出会う。そんな今の時代に合ったうつわ選びを叶えるヒントとして、二本柳さんにうつわ探しのアイデアと、注目のお店を教えていただいたので、次の章からご紹介していきます。
[うつわ探し のアイデア1]ゴールデンウィークは陶器市へ 「散歩がてらに近所のショップを見て回るほか、時間が許すならば春の陶器市へ訪れてみるのはいかがでしょうか」と二本柳さん。
「ゴールデンウィークは、多くの窯元や作家が参加する日本の2大陶器市と言われる『有田陶器市』と『益子陶器市』が開かれる タイミング。作家さんと直接お話をしながらうつわ選びができるのも魅力です。もちろんこの2つ以外にも、日本各地で陶器市は開かれています。訪れたいエリアで行われていないか調べて、旅行プランに取り込んでみるのもおすすめです」
日本最大級の陶磁器まつり「有田陶器市」
「有田陶器市」は、佐賀県有田町で毎年ゴールデンウィークに開催される日本最大級の陶器市 。1905年(明治38年)に、有田焼の販路拡大を目的に始まりました。有田焼は日本最古の磁器 として知られ、17世紀初頭に朝鮮半島から渡来した陶工によって生み出されたと言われています。
町中が会場となる陶器市。メインとなる有田駅~上有田駅までの道のりは約4km、約400の店舗が軒を連ねます。人気の西 隆行 をはじめとする多くの作家が出店し、作家と直接話しながら買い物ができる機会です。デザイナーズコラボのモダンな有田焼・2016/ や1616 、アリタポーセリンラボ から、老舗の源右衛門窯 まで。新旧問わず多くの窯元が出展し、初日から賑わいます。
また、朝早く訪れる人のために毎年用意される“朝がゆ”も人気 。有田館前の皿山商店会にて朝6時から、毎日限定300杯、1杯600円で提供されます。干支入り碗に入ったおいしい朝がゆをいただいたら、うつわをそのまま持ち帰れるのも魅力 。“朝がゆ碗”のみの販売も行われています。
町全体が賑わい、地元のグルメや体験イベントも充実。100年以上続く伝統を誇る有田陶器市は、全国から焼き物好きが集まるイベントで、掘り出し物や自分だけの理想のうつわに出会えるはず。
有田陶器市 HP
手作りの温もり・益子焼が堪能できる「益子陶器市」
栃木県益子町で開催される「益子陶器市」は、毎年春と秋に開催され、今回で111回目を迎えます 。町内の約50店舗が参加し、会場には600以上のテントを設置。伝統的な益子焼によるうつわから美術品まで、さまざまな作品を楽しむことができます 。
益子焼には、日常使いしやすいシンプルなデザインが多く、誰でも取り入れやすいのが魅力 。各テントでは、新進気鋭の作家や著名なアーティスト、窯元の職人たちと直接会話ができ、陶器市で作品を選ぶ醍醐味を味わえます。会場には、陶芸体験や絵付け体験ができるワークショップも開かれていて、益子焼の魅力を自ら体験することも 可能。
他にも、地元グルメやクラフト雑貨のマーケット、陶器市の会場各所や店舗で販売される、陶器市の公式オリジナルグッズも人気です。今回は、第111回を記念し、「碗3(ワンワンワン)ボールペン 」が発売されます。イラストを手掛けたのは、益子在住の作家・かとうゆみの さん。陶器だけでなく、旅の思い出になるアイテムに出会えるのも魅力です。
毎年春と秋を合わせて約60万人が訪れる、地域をあげた一大イベント。参加する作家や窯元の情報を事前にチェックして、お目当てを探しておくのもひとつの楽しみ方。事前の準備をしておけば、より満喫できるでしょう。
益子陶器市 HP Instagram
陶器市を120%楽しむための心得3つ 陶器市に行ったことがないという人も多いでしょう。初めて訪れる人に向けて、事前に用意しておきたいものや会場で気をつけたいことなど、陶器市を最後まで楽しむための心得を3つ教えていただきました。
心得1.エコバッグを持参
「購入したうつわを持ち帰るためのエコバッグを持参しましょう。割れやすいものを持ち帰ることになるので、薄めの生地よりもしっかりした生地のバッグがおすすめです。私はいつもエコバッグの底に気泡緩衝材を敷いてからうつわを入れ、割れないようにしています 」
心得2. 撮影の際には必ず許可をとる
「写真や動画撮影については、作家によりNGの場合もあるので、撮影前にお店の方に許可をもらうようにしましょう。撮影NGの方の作品を無断で撮っていて注意された、なんていうことがあれば、せっかくの陶器市も楽しさが半減。そうならないためにも、ひと声かけるようにしてくださいね」
心得3.体調管理に気をつけ る
「会期中はみなさんが予想している以上に混み合っています。とくに子ども連れの方は十分な水分を持参する など、準備をして行くと安全に楽しめるでしょう。ご紹介した有田や益子の陶器市のように、町全体が会場となる陶器市の場合、想定以上に歩き回ることになるので、スニーカーなどの歩きやすい靴で行く と安心です」
[うつわ探しのアイデア 2]ふるさと納税の返礼品で探す
ふるさと納税というと、お米やご当地グルメのイメージが普及していますが、実は、各地の窯元や作家のうつわも返礼品として登場しています。
「有田や益子はもちろん、日本各地のうつわが返礼品として取り扱われています。作家もののうつわの場合、まとまった数を取り扱っているお店は少ないのですが、ふるさと納税は自治体の活動ということもあり在庫の数も潤沢。「ふるさとチョイス 」や「さとふる 」でも特集ページがあるので、ぜひのぞいてみてください。よく見る有名なうつわも多数登場していますよ」
うつわのプロもお気に入り!ショップ3選 最後に、二本柳さんが実際に利用している、お気に入りのショップを3つ教えていただきました。
1.エディターならではのセレクションと発信力が光る!「IEGNIM」
編集プロダクションが運営しているお店。編集者ならではの取材⼒を活かし、全国の窯元へ直接出向き取材を重ね、現代のライフスタイルに合うものをセレクトしているそう。別注のオリジナルアイテムを含め、マグカップや植⽊鉢、カレーに使いやすい深⽫など、今の暮らしに馴染みやすいものが豊富に揃います。
古伊万⾥⾵の絵やポップな⾊遣いが⼈気の陶芸ユニット「studio wani 」や、九州を代表する⼩代焼の窯元・ふもと窯の若手・井上亮我 、1688年の開窯以来続く窯元「⿓⾨司焼企業組合 」など、全国から厳選されたうつわが並び、ストーリーを感じ取ることもできます。
↑左列が「studio wani」、中央の列が井上亮我、右列が「龍門司焼企業組合」の作品。
⻑い年⽉を重ね、多くの⽅に愛されている⺠藝品の魅⼒を発信するプロジェクトとしてスタートしたIEGNIM。名前の由来は、⺠藝のアルファベット“MINGEI”を逆から読んだもの。これまでの⺠藝の歴史をリスペクトしながらも、新しい価値観やスタイルを現代の⽣活様式に合わせて提案していきたいという想いが込められています。
ウェブサイトで配信される職⼈たちの世界観やストーリーを描いた記事も、編集プロダクションならでは。オンラインショップもあるので、遠方の人も買い物を楽しめます。不定期で開催される個展やイベントも人気です。
IEGNIM HP Instagram
【現在開催中の個展】 Instagram
2.店主がフランスをめぐり見つけたアンティークが揃う「BROCANTE」
店名のBROCANTEは、フランス語で“美しいガラクタ”や“愛すべき想いの詰まった古道具”を意味する言葉。店主がフランス全土を巡り心に響いたアンティークを、有名無名問わず紹介しています。
家具をはじめ、ヴィンテージの食器やオリジナルのリネン小物、ファブリックなど、生活に彩りを添える雑貨が豊富で、うつわとのコーディネートも楽しめます。長年大切に扱われてきたことがわかるシャビーな風合いと素敵な佇まいのアイテムに出会えるはず。
BROCANTE Instagram オンラインショップ
3.“つくる、たべる、もてなす”を特別に。和洋のうつわが揃う「TODAY’S SPECIAL」
東京都内と京都、神戸に8店舗を展開する「TODAY‘S SPECIAL」。今日が特別になるような発見ができる、食と暮らしのお店です。マーケットのようなにぎやかな店内には、生活道具や食材、植物や本、衣類などが並び、テーブルを飾る食器は和洋さまざまなものが揃っています。
日本各地の窯元で作られるTODAY‘S SPECIALのうつわは、土や釉薬、カタチ、技法など、細部まで相談を重ねて作られているそう。和洋各種のうつわのほか、調理道具や調味料など、世界中から集めた“つくる、たべる、もてなす”ことにまつわる商品が並びます。季節や旬を感じられる、フェアやワークショップなども行われているので、お近くのお店をチェックしてみてはいかがでしょうか。
TODAY’S SPECIAL HP
お気に入りのうつわがあれば、食卓が華やかになり食事の時間もより豊かに。うららかな春の日差しが心地よい日は、理想のうつわ探しに出かけてみませんか。
Profile
プロップスタイリスト・うつわ検定創設者 / 二本柳志津香 広告・CMをはじめ、ホテルや商業施設、展示会等のプロップ、テーブルスタイリスト。代表を務める空間スタイリング社では、フードからフラワーまでさまざまな空間スタイリストが在籍。日本で最初にできた食器のスタイリング資格を取り扱う、一般社団法人テーブルウェアスタイリスト連合会(TWSA)の代表理事も務める。著書『スタイリストが実践! 好きなものと上手につき合うインテリア』(主婦と生活社)、『うつわ検定公式テキスト 今の時代のうつわ選び』(主婦と生活社)がある。Instagram