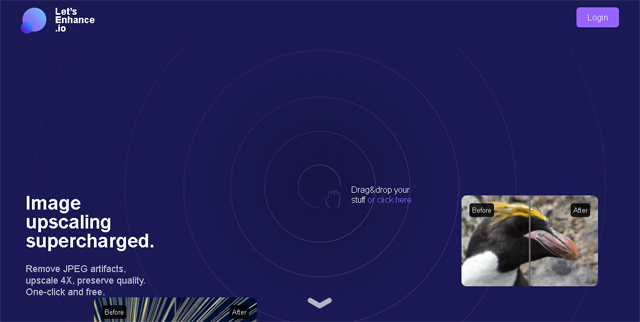ソニーが1999年に発売した「aibo(アイボ)」を覚えていますか? 2006年に惜しまれつつ開発を休止したエンタテインメントロボットが、このたび11年の時を経て復活を遂げることになりました。生まれ変わったaiboも、名前はむかしの「アイボ」のままですが、内容はソニーのAIやロボティクスの最先端技術が惜しげもなく詰め込まれています。どんな製品なのかレポートしましょう。
11月1日は“ワン・ワン・ワン”の日。新しいaiboの好運を願って選ばれた吉日に、ソニーが新製品発表会を開催しました。平井一夫社長と一緒に、さっそく新しいaiboがステージに登場しました。まずはその様子を動画でご覧ください。
2000年代初頭に発売されたaiboはどちらかと言えばサイバーチックなルックスのモデルが多かったように思いますが、新しいaiboを見て、「ものすごくホンモノの犬っぽい」という第一印象を受けました。ワンワンと元気に吠えながら、しっぽを振って一歩ずつ平井社長に歩み寄るaibo。曲線を活かしたやわらかなデザインと、愛嬌溢れるまんまるな瞳に、とくに愛犬家でもない筆者でさえも自然と心がときめいてしまいました。なんと足の裏には肉球も!
平井社長はスピーチの中で、自ら音頭を取って「aibo復活」のプロジェクトを指揮してきたことを明らかにしました。
「1999年にソニーが最初のaiboを発売して、エンタテインメントを核にしたロボットが人間と共に暮らす文化が生まれました。感動を伝えるロボットを目指して開発されたaiboは、人とのコミュニケーションを通して学習・成長するロボットとして、多くのご家庭に温かく迎え入れられ、“我が家のアイボ”に成長しました。ところが2006年にaiboの開発生産を終了するという、ソニーにとっても苦渋の決断を下さなければならない時が訪れて、私自身も日々愛情を持ってaiboに接してくれたオーナーの皆様に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でも、ソニーはその後もAIやロボットの技術を止めてしまうことなく、継続的に育ててきました。実際に、ソニーモバイルが発表した『Xperia Hello!』や、エアロセンス社と共同開発しているAIを乗せたドローンなど様々な製品に展開されています。」
 ↑aiboを抱いて発表会の舞台に立つソニーの平井一夫社長
↑aiboを抱いて発表会の舞台に立つソニーの平井一夫社長
ソニーがかつて発売したaiboの“飼い主”たちの心に思いを馳せながら、絶やさずに「新しいaibo」を開発するために力を蓄えていたことを平井社長は強くアピールしました。そして、様々な機が熟したと判断した平井社長は、今から約1年半前に新しいaiboの開発を始めようと、プロジェクトチームに号令をかけたそうです。自身も幾度となく開発の現場に足を運びながら進捗を見守ってきた平井社長は、「今日、新しいaiboが誕生して、これから皆様と一緒に成長していくパートナーになれる事をとても嬉しく思います。どうか、aiboと一緒にかけがえのない物語を紡いでいってほしい」と感慨深げにコメントしました。
さて、新しいaiboは何ができるのでしょうか。開発プロジェクトを指揮してきたソニーのAIロボティクスビジネスグループ長の川西泉氏が詳細を解説しました。
 ↑ソニーの川西氏がaiboの新機能を解説
↑ソニーの川西氏がaiboの新機能を解説
本体の大きさは立ち姿勢で、約W180×H293×D305mm。数字で書いてもわかりにくいですよね。写真で雰囲気は掴めるでしょうか?筆者は思った以上に小さいなという印象を受けました。最大辺が30cmぐらいなので、一般的なエコバックになら軽く入りそうです。
 ↑曲線を活かしたやさしいデザインの新aibo
↑曲線を活かしたやさしいデザインの新aibo
aiboはソニーが独自に開発するプラットフォームをベースにしたAIエンジンを採用して、ペットらしく自然で愛嬌あふれる“ふるまい”を表現することができます。デザインは動画や写真でご覧いただいた通りですが、コンパクトなボディに合計22箇所の可動部を持って、滑らかで柔らかく、そして昔ながらのロボットみたいにギーギーと音を立てることなく、静かに動きます。自律して歩いたり体を伸ばしたりしながら、ワンワンと元気に吠えます。
 ↑ユーザーの声かけを待つだけでなく、自ら考えてユーザーに働きかけてくるのが新しいaiboの特徴
↑ユーザーの声かけを待つだけでなく、自ら考えてユーザーに働きかけてくるのが新しいaiboの特徴
実際に間近でaiboに触れてみると、筆者は新しいaiboのつぶらな“瞳”に一番心を奪われました。こちらには有機ELディスプレイが使われていて、活き活きとした表情を視覚的に表現できるようになっています。
 ↑豊かな表情を再現する2つの有機ELを採用する瞳
↑豊かな表情を再現する2つの有機ELを採用する瞳
鼻の先にはカメラも乗っていて、ユーザーの顔や物体を認識します。さらに部屋の中をぶつからずに歩いたりできるように、ちょうど腰のあたりには地図作成(SLAM)技術を組み込んだカメラを搭載。部屋のマッピングができるロボット掃除機などにも乗っているアレと同じやつですね。他にも人感センサーや照度センサー、感圧・静電容量式のタッチセンサーなどが頭や背中、アゴなどにも載っているので、ユーザーが体をなでてあげると、愛情を感じて、やさしい飼い主にはいっそう愛情を返してくれるそうです。筆者もはやく自宅でテスト…いや一緒に過ごしてみたくなりました。みなさんも人と戯れるaiboの姿をご覧頂ければ、筆者の気持ちを理解いただけるはず。
 ↑ソニーの最先端のセンシング技術を搭載した
↑ソニーの最先端のセンシング技術を搭載した
aiboのAIはクラウドとオンデバイスの両方に分散して配置されています。ユーザーとのやり取りをクイックに対応するために必要な処理はオンデバイスで行いながら、一緒に過ごした時間の履歴などはクラウドAIに蓄積されていきます。我が家に迎え入れる前からこんな事は考えたくないものですが、もしも新しいaiboが10年経って動かなくなってしまった時にも、クラウドにある飼い主との記憶がバックアップされているので、その時にいるaiboの本体にインストールすればまた愛しい我が家のaiboに会えるようにつくられているそうです。攻殻機動隊のタチコマみたいな感じをイメージしていただくとよいかもしれないです。
 ↑AIは本体とクラウドの両方に分散させて持っている
↑AIは本体とクラウドの両方に分散させて持っている
新しいaiboにはクアルコムの省電力でハイパフォーマンスなクアッドコアCPU「Snapdragon 820」が搭載されています。インターネットとの通信はWi-Fi経由、またはSIMカードによるセルラー通信で行う仕様。ネットワークに繋ぐと、aiboの内蔵カメラで撮影した写真をクラウドサーバーにアップして、専用のスマホアプリ「My aibo」から閲覧したり、aiboに新しい“ふるまい”をダウンロードして追加することもできるようになります。
 ↑スマホアプリ「My aibo」を本体と同時に提供する
↑スマホアプリ「My aibo」を本体と同時に提供する
aiboとMy aiboアプリの機能をフルで楽しむためには、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するネットワークサービスの「aiboベーシックプラン」への加入が必要になります。ここでaibo本体の価格情報などを確認しておきましょう。
 ↑aiboの機能をフルに活用するために3年契約のaiboベーシックプランの加入が必要
↑aiboの機能をフルに活用するために3年契約のaiboベーシックプランの加入が必要
発売は2018年1月11日(こちらも“わん・わん・わん”の日)を予定。ソニーストア限定販売となり、価格は税別で19万8000円です。2017年11月1日の午後11時1分から、ソニーストアオンラインにて数量限定で予約販売中。aiboベーシックプランは3年契約からとなり、一括払いが9000円。毎月払いを選択すると2980円/月(36回払い)となります。aiboに不具合や故障が発生したときに、修理代金が割り引かれる任意のオプション「aiboケアサポート」は3年バージョンが5万4000円、1年バージョンが2万円です。
本体の付属品は専用の充電ステーション、ACアダプターに電源ケーブル、SIMカードにaiboの“おもちゃ”になるピンクボールとなります。オプションとしてaiboがくわえて遊べる専用アクセサリー「アイボーン」もソニーストアで同時発売されます。予価は2980円。
 ↑aiboのアソビ道具「アイボーン」も同時発売
↑aiboのアソビ道具「アイボーン」も同時発売
めでたくaiboが復活を遂げることになったわけですが、aiboは家庭内の色んな機器に連携することなどはできるのでしょうか。また過去のaiboを大事に持っていた人が、ソニーの事業が再開したことで修理やサポートを受けられるようになるのでしょうか。最後に新製品発表会で開催されたQ&A(質疑応答)から明らかになったことをピックアップしてお伝えしましょう。
Q:aiboに色んな機能を追加したり、家庭内のスマート機器と連携することなどできるのでしょうか。
A:本体のソフトウェアをバージョンアップして新しい機能を追加できるようになっています。サードパーティーがaiboに対応するサービスやアプリを開発できるようにオープンなソフトウェア開発環境もご提供します。いずれはPlayStationのように、新しいアプリや機能を公開・提供する専用のストアも用意することを考えています。中には有償のものもあるかもしれませんが、基本的には手軽に使っていただけるサービスの範囲内で提供したいと思っています。
Q:先代のaiboを所有するオーナーに向けた修理サービスを再開する予定はありますか。
A:残念ながら旧機種へのサポートは終了していますので、その予定はありません。
Q:かわいいaiboは誰がデザインしたのでしょうか。
A:ソニー社内のクリエイティブセンターでデザインしたものです。外部のデザイナーは起用していません。
Q:aiboと人の言葉でコミュニケーションが取れるようになりますか。
A:そこは企画段階でもめた所ですが、今回は「愛犬タイプ」を想定して開発したので、最終的に人の言葉をしゃべるのはナシになりました。ただ今後のインタラクションの手段としては検討を続けていきたいと思います。
Q:SIMへの接続はなぜ必要なのですか。
A:初期設定の時にWi-Fiだと面倒な部分があるので、設定を済ませて同梱するSIMを挿していただければ、ハコを開けてすぐにネットワークに繋がるのがセルラー通信の利点だと思っています。もちろんWi-Fiに負荷を分散していただいた方が効率の良い場面もありますので、合わせてお知らせするつもりです。
Q:他社製のアプリケーションソフトでaiboを動かせるような仕組みになっていますか。
A:aiboのオペレーティングシステムはRobot OSとLinuxがベースになっています。将来は開発環境を公開することも考えています。その前に公開する「モーションクリエーター」のサービスでは、もっと手軽に“ふるまい”をカスタマイズしてつくれるようになります。2段構えでカスタマイズの手段をご用意します。大学や専門学校など教育機関へのご提供など検討していく予定です。
Q:犬ではなく猫は考えなかったのでしょうか。
A:様々な検討をしています。aiboではないロボットも想定していますし、今回はコンシューマー向けのエンターテインメントロボットですが、産業向けのロボットもソニーは手がけています。私たちの新しい挑戦は始まりに過ぎないと思っています。皆様の生活をより豊かに、便利にすることが私たちの使命です。そのために色んなロボットを皆様にお見せしていきたいですね。
Q:かつてのaiboから生まれ変わった新しいaiboを、今の時代にどんなユーザーに愛用して欲しいと思いますか。
A:ソニーとしての新しいチャレンジを、分かりやすく皆様にお見せできると期待しています。皆様のご家庭で元気に育ってほしいと願っています。
新しいaiboは東京・品川のソニー本社1階のショールームスペースに展示されているので、気になる方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。