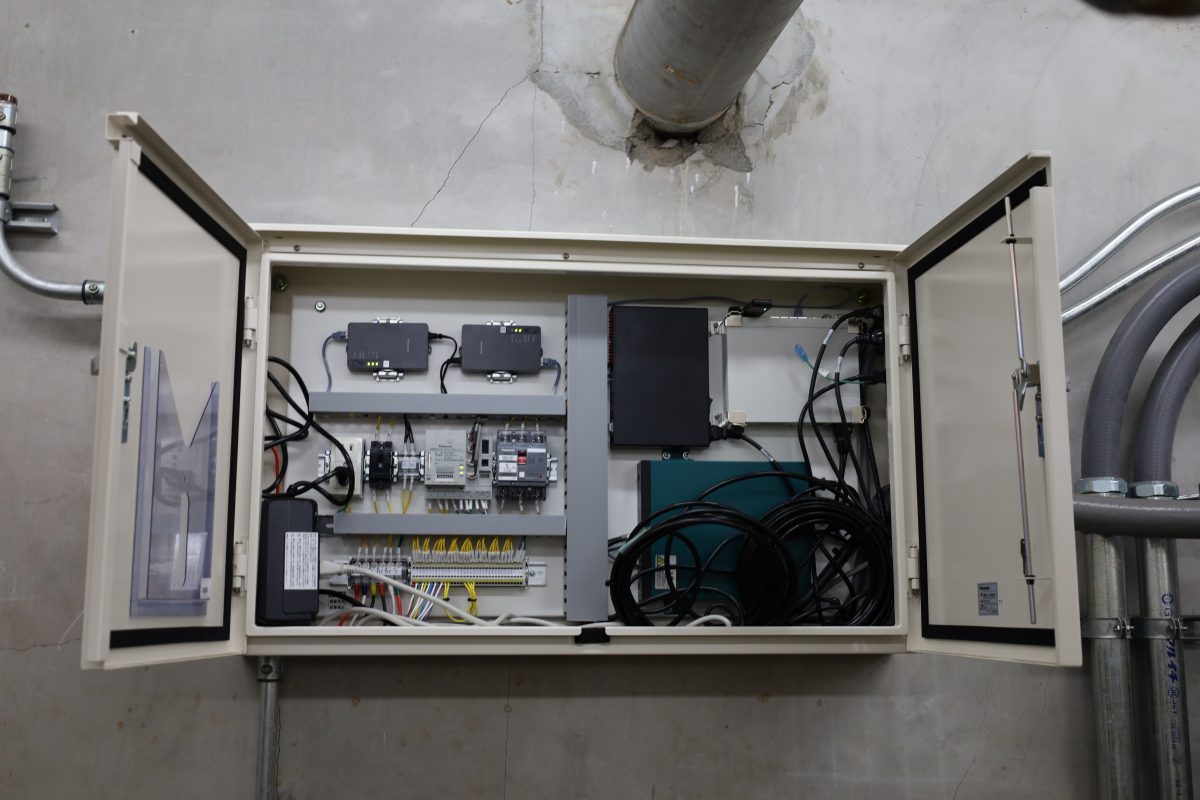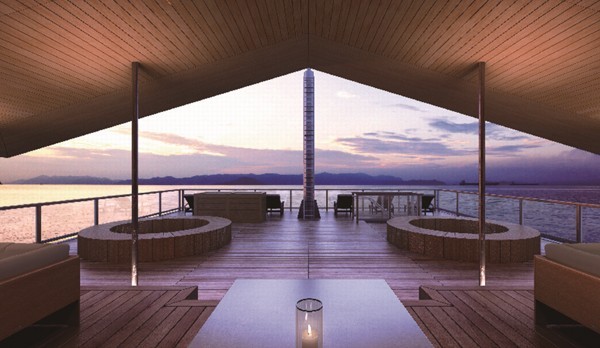相模灘を眼下に望む東海道本線の早川駅〜根府川駅間のカーブを、うねるようにして貨物列車が進む。ブルートレイン牽引機として活躍したEF66 “マンモス”、その血を受け継いだJR貨物のEF66形式直流電気機関車が、長い貨物列車の先頭に立つ。24両編成、総重量1000トン以上にも及ぶコンテナ貨車。力強く牽引する姿は豪快そのものだ。

この貨物列車の姿のように、JR貨物がいま、力強く元気だ。長年、赤字体質だった会社が、6年前から黒字経営に、さらにここ数年は好業績を上げ続けている。どのようにして体質改善が図られていったのか、変わるJR貨物の現状を見ていきたい。
6年連続増益!ついに最高益をあげるまでに
まずは、JR貨物の好調ぶりを数字で見ていこう。
平成29年10月30日に、平成30年3月期の中間決算が発表された。営業収益は935億円。対前年比23億円プラスで、2.6%の増収となった。営業利益にいたっては前年比12.2%増、経常利益は対前年比20.5%増となった。
中間期の純利益を見るとなんと78.2%の増加となる。これで6年連続増益となり、中間期決算の公表を開始した平成9年度以来の最高益をあげた。
 ↑JR田端駅近くビル上にある案内看板。夜になると機関車のヘッドライトが光り、面白い。赤い電気機関車がJR貨物を力強く牽引するといった構図にも見える
↑JR田端駅近くビル上にある案内看板。夜になると機関車のヘッドライトが光り、面白い。赤い電気機関車がJR貨物を力強く牽引するといった構図にも見える
いまでこそ好調のJR貨物だが、10年ほど前まで、この状態はとても予想できなかった。純利益を見ると、平成20年度(△15億円)、21年度(△27億円)とマイナスの数字が並ぶ。22年度(10億円)は持ち直したものの、東日本大震災があった平成23年度はマイナス5億円の損失を計上した。
ところが、翌平成24年度からプラスに転じ、それ以降、ほぼ右肩上がりで業績を延ばしている。
こうした背景には、トラック輸送から鉄道輸送や船輸送への転換。CO2の排出を減らそうとする取り組み「モーダルシフト」が、国により強く推進されたこともあるだろう。また昨今の、ドライバー不足から鉄道貨物輸送への転換を余儀なくされた荷主が増えている背景もありそうだ。
一方で、時間をかけつつも、より効率の良い鉄道貨物輸送を目指してきた、その成果が実を結んだようにも思える。どのような改善を施し、また成果を生み出したのか、いくつかの事例を見ていきたい。
【事例①】
企業とのつながりを強めた「専用列車」の運行
鉄道貨物の輸送は大きく2つにタイプに分けられる。「車扱(しゃあつかい)輸送」と「コンテナ輸送」の2つだ。石油や鉱石などを専用の貨車に載せ、走らせることを車扱輸送と呼ぶ。一方、一定の大きさのコンテナを貨車に載せて運ぶ列車をコンテナ輸送と呼ぶ。
古くは車扱輸送が主流だったが、現在は、コンテナ輸送が鉄道貨物全体の約70%を占めている。主流となるコンテナ輸送だが、その姿を大きく変えたのが次の列車だった。
 ↑一企業の専用列車として走り続ける「スーパーレールカーゴ」。東京貨物ターミナル駅を23時14分に発車、大阪の安治川口駅に早朝5時26分に到着する
↑一企業の専用列車として走り続ける「スーパーレールカーゴ」。東京貨物ターミナル駅を23時14分に発車、大阪の安治川口駅に早朝5時26分に到着する
2004(平成16)年に走り始めた「スーパーレールカーゴ」。東京貨物ターミナル駅と大阪市内の安治川口駅を結ぶ貨物列車で、佐川急便の荷物を積んだコンテナのみを載せて走る。
M250系という動力分散方式の車両を利用、専用のコンテナを積んだいわば“貨物電車”のスタイルで走る。深夜の東海道本線を最高時速130kmで走り、上り下りとも約6時間10分で結ぶ。深夜に出発して、翌早朝には東京、大阪に到着するダイヤで運行されている。
「スーパーレールカーゴ」での輸送が実績を上げたこともあり、2013年からは福山通運の専用列車「福山レールエクスプレス号」が東京貨物ターミナル駅〜吹田貨物ターミナル駅(大阪府)間を一往復しはじめた。さらに「福山レールエクスプレス号」は、2015年から、東京貨物ターミナル駅〜東福山駅(広島県)間、2017年には名古屋貨物ターミナル駅〜北九州貨物ターミナル駅間の運行も開始された。こうした専用のコンテナ列車は、1往復で、大型トラック60台分のCO2削減につながることもあり、効果が大きい。
 ↑東海道貨物線を走る「福山レールエクスプレス号」。同列車は東京〜大阪間だけでなく、東京〜福山間、2017年5月からは名古屋〜北九州間の運転も始まっている
↑東海道貨物線を走る「福山レールエクスプレス号」。同列車は東京〜大阪間だけでなく、東京〜福山間、2017年5月からは名古屋〜北九州間の運転も始まっている
この動きは、宅配業種との協力体制のみに留まらない。2006年11月から運行を始めたのが「トヨタ・ロングパス・エクスプレス」。列車名でわかるように、トヨタ自動車関連の部品類を運ぶ専用列車だ。愛知県の笠寺駅(名古屋臨海鉄道・名古屋南貨物駅着発)〜盛岡貨物ターミナル駅、約900km間を約15時間かけて走る。1日に2往復(土・日曜日は運休)するこの専用列車。愛知県内にあるトヨタ自動車の本社工場と岩手工場間の部品輸送に欠かせない列車となっている。
 ↑相模灘を背に走る「トヨタ・ロングパス・エクスプレス」。青い色の31フィートサイズの専用コンテナを積んで走る
↑相模灘を背に走る「トヨタ・ロングパス・エクスプレス」。青い色の31フィートサイズの専用コンテナを積んで走る
2018年3月のダイヤ改正からは、こうしたクルマの部品輸送用の専用列車が相模貨物駅(神奈川県)〜北九州貨物ターミナル駅間を走る予定で、専用列車の需要はますます高まっていくと言えそうだ。
【事例②】
スムーズな輸送に欠かせなかった拠点駅の整備
専用列車の登場とともに、JR貨物のスムーズな輸送に大きく貢献したのが2013年3月の吹田貨物ターミナル駅の開業だ。国鉄時代には、東洋一の規模を誇った吹田操車場の跡地の一部を利用した貨物駅で、東海道本線の千里丘駅〜吹田駅間の約7kmにわたる広大な敷地に貨物ターミナル駅が広がる。
 ↑東海道本線に沿って設けられる吹田貨物ターミナル駅。同駅の整備にあわせて福山通運の「福山レールエクスプレス号」の運行が始められた
↑東海道本線に沿って設けられる吹田貨物ターミナル駅。同駅の整備にあわせて福山通運の「福山レールエクスプレス号」の運行が始められた
同駅の整備により、先にあげた「福山レールエクスプレス号」などの列車の着発と、荷役が可能になった。また貨物列車の上り下り線ホームを整えたことで、東海道本線や山陽本線という物流の大動脈を走る列車の荷役作業を、よりスピーディに行えるように改善された(作業は着発線荷役と呼ばれる)。
吹田貨物ターミナル駅からは、大阪市内の別の貨物駅、大阪貨物ターミナル駅や百済貨物ターミナル駅を向かう列車も多い。構内を整備したことで、これらの列車の発着もよりスムーズになった。1つの駅の整備が大阪圏内だけでなく、西日本の鉄道貨物の流れをよりスムーズにしたと言っても良いだろう。
 ↑東海道本線を走る多くの貨物列車の起終点となるのが東京貨物ターミナル駅。駅構内に新たに設けられる大型物流施設の工事も始まっている
↑東海道本線を走る多くの貨物列車の起終点となるのが東京貨物ターミナル駅。駅構内に新たに設けられる大型物流施設の工事も始まっている
【事例③】
引っ越し需要にこたえて臨時列車を走らせる
3月、4月は1年で、最も引っ越し需要が高まる季節。さらに今年はドライバー不足、働き手不足の影響もあって、引っ越し料金が高騰し、予約が取れない状況だとされる。
そんな引っ越し需要に合わせて、JR貨物では3月上旬〜4月上旬にのべ30本の臨時列車を運転、68本の貨物列車の曜日運休を解除して、12フィートコンテナ換算で9800個(49,350トン)の輸送力の増強を図っている。
臨時列車が走るのは大阪貨物ターミナル駅〜鳥栖貨物ターミナル駅(佐賀県)・北九州貨物ターミナル駅間や、隅田川駅(東京都)〜札幌貨物ターミナル駅間。こうした柔軟性に富んだ対応も、JR貨物の新しい一面と言えるだろう。
【事例④】
国鉄時代に生まれたコンテナ貨車が消えていく
コンテナを積む貨車の更新も改善されてきたポイントの1つだ。
コンテナ用の貨車は1970年代にコキ50000形式が大量に造られた。その後、1980年代の終わりに、コキ100系というコンテナ貨車が生まれた。
40年にわたり使われてきたコキ50000形式だったが、時速100〜110kmのコキ100系に対して、最高時速が95kmと見劣りした。しかも床面の高さがコキ100系の1000mmに比べ1100mmと10mmほど高い。コンテナ貨車はコンテナを積んだときに、上限となる限界値があり、コキ50000形式には背の高いコンテナを載せることができない。
 ↑1970年代に大量に造られたコキ50000形式。高床構造で、12フィート汎用コンテナの利用の場合、高さ2500mm未満の限定サイズを使わざるを得なかった
↑1970年代に大量に造られたコキ50000形式。高床構造で、12フィート汎用コンテナの利用の場合、高さ2500mm未満の限定サイズを使わざるを得なかった
いままで使われ続けてきたコキ50000形式だったが、2018年3月のダイヤ改正で残っていた車両が消えることになった。
今後、コンテナ貨車は、ほぼコキ100系に統一される。これまで12フィートサイズの汎用コンテナは、コキ50000形式に合わせてつくられていた。しかし、コキ100系が主流となることで、高さを2500mmから2600mmへと、100mmほどサイズが大きい汎用コンテナが一般化することになる。わずか100mmの違いながら、それだけ多くの荷物の積み込みが可能になるわけで、荷主にとってありがたい改善点となる。
 ↑31フィートコンテナを載せたコキ100系。高さが2500mmを越えるコンテナには、誤った積載を防ぐため「コキ50000積載禁止」の文字が書かれていた。
↑31フィートコンテナを載せたコキ100系。高さが2500mmを越えるコンテナには、誤った積載を防ぐため「コキ50000積載禁止」の文字が書かれていた。
【事例⑤】
鉄道ファン受けしそうな貨物用機関車の塗り替え
最後に鉄道ファンとしては気になる貨物用機関車の話題に触れておこう。この貨物用機関車の運用に関しても、現在のJR貨物らしさを見ることができる。
EF200形式直流電気機関車という強力な貨物用機関車が使われている。東海道・山陽本線で使われる機関車で、日本の機関車史上、最強の6000kWの出力で、1600トンの貨車の牽引が可能な車両だった。
この機関車はJR貨物発足後の1990(平成2)年、景気が良かった時代に誕生した。ところが、生まれたあとの輸送需要が伸びなかったこと、フルパワーで走ろうとすると、地上の変電設備などに負荷をかけることから、出力を抑えての運転が余儀なくされていた。問題をかかえていたために21両と製造数も少なかった。
生まれてまだ30年も経っていないが、すでに稼働しているのが4両のみとなっている。このままでは、あと数年で消えていきそうな気配だ。
 ↑日本の電気機関車史上、最大のパワーを誇ったEF200形式電気機関車。オーバースペックがたたり、国鉄形機関車よりも先に消えていきそうな気配だ
↑日本の電気機関車史上、最大のパワーを誇ったEF200形式電気機関車。オーバースペックがたたり、国鉄形機関車よりも先に消えていきそうな気配だ
消えていきそうな機関車がある一方で、国鉄形電気機関車に面白い動きが見られる。
国鉄がJRに分社化されすでに30年あまり。JR貨物に残る国鉄時代生まれの機関車も減りつつある。そんな動きのなか、国鉄形機関車のなかに、全般検査を受け、今後、3年、5年と走り続けそうな車両も出てきた。EF64形式やEF65形式が昨年から数両、全般検査を終えて工場から出庫してきているが、塗り替えた姿は、両形式ともすべてが国鉄原色と呼ばれる塗装だった。
 ↑EF65形式直流電気機関車の2065号機。定期的に行われる全般検査の際に国鉄原色に戻され、鉄道ファンの心をくすぐった
↑EF65形式直流電気機関車の2065号機。定期的に行われる全般検査の際に国鉄原色に戻され、鉄道ファンの心をくすぐった
まさか、鉄道ファンに人気だから、ということでの国鉄原色への回帰というわけではないだろう。とはいえ、貨物ターミナル駅や機関区などの公開イベントなどでは、親子連れを含め多くの人が集まり、JR貨物の人気は高い。塗装変更という1つの現象ではあるものの、こうしたJR貨物へ興味を持つ鉄道ファンに受けるがための塗りかえであったら歓迎したい。
 ↑EF64形式の国鉄原色機は一時期、消えてしまった(JR貨物の場合)。ところが1028号機が全般検査後に国鉄原色に戻された。この復活劇を喜んだ鉄道ファンも多い
↑EF64形式の国鉄原色機は一時期、消えてしまった(JR貨物の場合)。ところが1028号機が全般検査後に国鉄原色に戻された。この復活劇を喜んだ鉄道ファンも多い
 ↑JR貨物のEF64形式といえばブルーに白のラインの色分けが多い。鉄道ファンからは“牛乳パック”と呼ばれたカラーだが、今後、この塗り分けはどうなっていくのだろうか
↑JR貨物のEF64形式といえばブルーに白のラインの色分けが多い。鉄道ファンからは“牛乳パック”と呼ばれたカラーだが、今後、この塗り分けはどうなっていくのだろうか