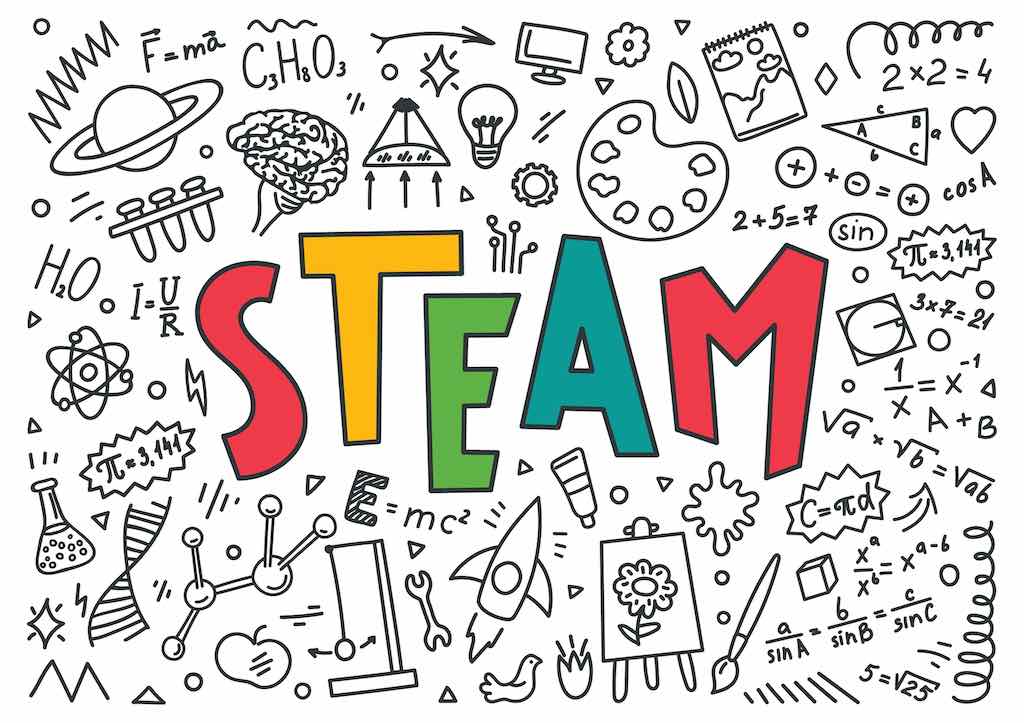インドでは2020年7月から、新たな「国際教育政策(NEP2020)」が施行されています。教育政策の見直しは30年ぶりのことでしたが、その主眼は個人の能力を伸ばし、IT発展後も世界で活躍できる人材を育てること。「公平でインクルーシブな教育」を重要視しながら、誰もが質の高い教育を受けられることを目指します。今後の課題についても触れながら、インドの教育現場がどのように変化しつつあるのかを説明します。

3歳からの早期教育を重視
まず大きく変わったのは、早期教育に重点を当てる教育制度になったこと。従来の教育システムでは6歳から始まる「10・2年制度」でした。今回の改訂では「6歳以前から脳の発達が育まれる」という考えに基づきながら3歳からの早期教育を導入し、「5・3・3・4年制」を採用。新しい教育システムによると、子どもたちは基礎段階で5年間、準備段階で3年間、中期段階で3年間、中等教育段階で4年間を過ごします。
現在、幼児はまず近くのプレスクールで日中を過ごし、4歳ごろになると幼稚園で2年間を過ごします。そして、就学開始時の6歳になると小学校に入学するのが一般的です。経済的な理由から、幼稚園には通わずに就学する子どもも多くいます。
インド政府は言語習得をはじめ、数字に関する感覚の基盤がないとその後の学習に大きく影響すると考え、言葉が発達する幼児期の教育が大切だと判断。政策の見直しにより、3歳から教育を受け始めて8歳まで同じ学校で学び続けることができるようになりました。新しい教育政策によって、基礎段階である幼稚園から小学校低学年まで一貫した教育を5年間受け、その後中等教育への準備段階にあたる小学校高学年の学習を3年間受けるという形になったのです。
3歳からの義務教育化によって有料の幼稚園やプレスクールに通わせる必要もなくなり、教科書代などを除けば基本的に教育費用は無料。さらに、統一されたカリキュラムに沿って授業が行われるようになり、どの子も公平に教育を受けることが可能となりました。

暗記学習からSTEAMへ
また、新たな教育政策では個人の能力を伸ばす方向へと舵を切ったことも特徴。そのために、これまで暗記学習主導だったカリキュラムを体験学習や応用学習、分析・探求学習、STEAM教育を意識した学習へと移行しています。
これまでインドの教育は暗記中心型で、20段まである掛け算の九九も言えるなど九九や数式などの暗記を重視してきました。暗記ができた生徒から黒板の前に立って全員の前で暗唱し、できなければ覚えるまで続けるなどの手法で、他の科目も同様でした。
しかし今後は、新たな教育政策のもとで、暗記中心の教育から、個人の能力を伸ばす教育に転換していくことになります。具体的には、個人が抱く関心や興味を大切にし、批判的思考も養いながら、ディスカッションを通して学んでいく手法を導入。例えば、地球温暖化など自分が興味を抱いた一つのテーマについて自由に調べたうえで意見を発表し、さらにクラス内で意見交換するなど、従来の受け身から自らが進んで学ぶといった学習に変化します。
また、職業学習、数学的思考、データサイエンスやコーディングなど最新のデジタル技術を用いた体験学習を導入すると同時に、新たに科目選択制ができるようになり、芸術や体育など副教科とされるものについて自分の興味のある科目を選択できるようになりました。
教員側には、生徒の教育的、肉体的、精神的な満足度や幸せを対象に含めた新たな評価モデルが取り入れられていますが、これら全ては、将来に備えて子どもたちを真のグローバル市民に育て上げることを目標に設計されているのです。

質の高い教員の確保が課題
新しい教育政策を進めていくうえで重要になるのが、教師の存在です。「NEP2020」を背景に、2022年1月から国内45の教育機関が新たな「統合教師教育プログラム(ITEP)」を開始しました。質の高い教師の育成に向けたもので、「ITEP」のコースは全国共通入学試験や教育技術評議会のスコアに基づいています。
これまで教師を目指す人は卒業と学士号取得まで5年間かかるなど、日本の大学の教職課程よりも長かったのですが、ITEPの学士号プログラムでは4年間に短縮。才能のある若者などにとって大きなメリットになると言われており、2030年以降はITEPが教師採用の基準になるようです。
しかし、インドでは教師の給与は高いとはいえず、むしろ低賃金の職業とされています。NEP2020によって700万人以上の教師が必要になると推定されていますが、どのように優秀な人材を確保していくのかが今後の重要課題です。
新たな政策のもと、大きく変わりつつあるインドの教育。筆者が知る学校では3歳からの早期教育プログラムが始まっており、子どもたちは自然の中で学習したり、造形活動をしたりと五感を使って楽しそうに学んでいます。社会的・経済的階級や背景に関係なく、全ての子どもが公平に質の高い教育を受けられるようになることは、格差社会を改善する第一歩となるでしょう。
執筆/流田 久美子
読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ
『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。
なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。